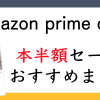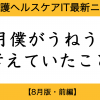2020年について、いま思うこと
ようやく2020年が終わった。近年稀に見る、長い一年だったように思う。
また、自分が生まれて数十年の間で、忘れがたい、象徴的な一年だったなと思う。
なんだっけ、10年に1度起こる、なんとかの革新みたいなやつ。
まあそれは重要ではないとして、僕(あるいは僕たち)の人生において、およそ10年に一度こういうことが起こるのだ。
それは、例えば2000年くらいのインターネット(世間的には95年くらいだったと思うが、自分史的には2000年くらいがピークだった)であり、2011年の東日本大震災だった。
震災のとき、僕はリクルートの36階のビルにいて、あまりにも揺れて、この高層ビルが、ポキっと折れるのかと本気で思った。こんなふうにして、人は突然に終わるのか、と。
窓の前から見えるお台場が火の海になって、世界の終わりとはこういうことかと思った。
そして、2020年、新型コロナの流行が起こった。
仕事柄、僕のまわりは、医療者もたくさんいる、知り合いでCOVID-19陽性になった人もわずかではあるがいた(Facebookなどで知ったという程度だが)、飲食店をやっている友人もいるし、最初の仕事の関係で旅館業界の人の声も多く聞いた。もちろん、映画産業にいる友人も多い(御存知の通り映画業界は崩壊だ)。
また、日本中を旅しながら仕事をしたことで、毎夜居酒屋で飲み歩いたので、地域の飲食店や観光産業の声も多く聞いた。
自身が経営する会社にあたっては、どんなことがあってもなんとかしなければいけないともがいた。そして、色々はあれど、なんとかやっていけている(と思う。勿論まだどうなるかわかんないけど、なんとかする。それはただ、覚悟だ。)
でも、世の中には、移行がどうしたって成立しない業界もある。
人が外に出なければ、死んでしまう会社は多数ある。
一度会社の倒産を経験した身としては、その辛さは言葉にするのも憚られるし、僕は、今もそうなった/そうなろうとしている人の存在に自覚的にありたい。
今年は、普段頭がいいな、凄いなと思う人たちからも、自分と無関係な世界に対して、あまりにも認識していないなと思わされる発言を目に/耳にして悲しくなる瞬間が少なくなかった。(その多くは、この感染症によって、ネガティブな影響を受けていない人たちから発せられたものだ)
自分の立ち位置を俯瞰して見ることが求められた一年だった。
ともすれば、簡単に自分(たち)と自分(たち)以外というグループを作って、「共通の敵」をつくってしまうことが非常に簡単にできてしまう一年だった。むしろ意識的にいないと、そうなってしまうのが自然だった。
「こんなときに外に出るやつは頭がおかしい、医療崩壊になってしまってもいいのか」という声が右から聞こえたら、同じタイミングで、「人が外に出なければ僕たちの会社はお店はどうするんだ? ここで生きている人たちのことを考えろ」 という言葉が左耳から聞こえてくる、ということが日常に起こっていた。
誰も「この世界を崩壊させてやろう」「あいつを貶めてやろう」と悪意があって言っているわけではない。
それぞれ誰もが、自分の立場で真剣に考え、正しいと思うことを言っているだけなのだ。
2020年、僕はたまたま、この位置にいたのだ。
もしかしたら、医療側とコロナで影響を受ける産業側の両方に深く接する立場にいる人は決して多くないのかもしれないと思った。
それまで、スタンスをとることは大切だと思ってきたが、その両方の立場を知る今日の状況においてだけは、スタンスをとることは、ともすれば、非常に危険な、意図しない結果を招くことになるなと思った。
あるとき、僕は新型コロナについて自分のポジションを発することを止めた。ポジションをとって発言すれば、それがどんな内容であれ、誰かの一時的な満足を生み出すかもしれないが、同時に不幸になる人をつくってしまうと思って怖くてしょうがなかった。
私は真剣に、ストラグルして自分の人生を生きるすべての人に尊敬の念で接したい。
不真面目な態度なんて、それが仕事でも、遊びでも、どんなことであれ犬に喰わせてしまえ、と思っているが、2020年ばかりは、不真面目な態度で生きている人は限りなく少なく見えたのだ。
真面目に生きる人を、無自覚に傷つけることはしたくない、と強く思った。
そして、こういうときにとるべきアプローチは、思考の限界ギリギリまで、自分(たち)を俯瞰・相対化して見ることだと考えた。
自分を俯瞰/相対化するにあたって、「サイズとスケール」という言葉が最近とてもしっくりきている。
「サイズ」は、たとえば「1cm」という絶対化されたものであるが、その「1cm」の価値は、人の生き方や、立ち位置、そして時間軸において変わる/変えることができるというのが「スケール」の発想だ。
いまこそ世界で起こっていることを、「サイズ」ではなく「スケール」を変えて考えることが必要だと感じた。それはすなわち、いま起こっていることを点で捉えずに、「人類全体」や「人類史」という視点を内在化するということだ。
2020年、映画ベスト
さて、本記事は、2020年の映画ベスト10である。
映画は本当に見る数が減った。理由は、いろいろある。
新作は本当に減った、映画館は封鎖されてしまった(僕は新作は映画館で見たい信者だ)、大自然リモートと称して、物理的に東京にいなかったことが多かったことも大きい。
しかし、今年も12歳くらいのときから、一度だって変わらず、全く同じように映画に救われた。数は少ないけれども、忘れがたい映画や映画体験と出会った一年だった。今年、それでも映画を作り続けたあなた、そして映画館で上映を決め、届けてくれた、あなたたち全てのおかげで、僕は前を向いて生きていける。
そんな、一年において、もっともアクチュアルに響いた10本、愛してやまない順。
1. 『ストーリー・オブ・マイライフ / わたしの若草物語』(グレタ・ガーウィグ、アメリカ)

2. 『WAVES』(トレイ・エドワード・シュルツ、アメリカ)

3. 『mid90s ミッドナインティーンズ』(ジョナ・ヒル、アメリカ)

4. 『燃ゆる女の肖像』(セリーヌ・シアマ、フランス)

5. 『ブックスマート』(オリヴィア・ワイルド、アメリカ)

6. 『リチャード・ジュエル』(クリント・イーストウッド、アメリカ)

7. 『スパイの妻』(黒沢清、日本)

8. 『TENET テネット』(クリストファー・ノーラン、アメリカ・イギリス)

9. 『行き止まりの世界に生まれて』(ビン・リュー、アメリカ)

10. 『ミセス・ノイズィ』(天野千尋、日本)

さて、短いながらも、それぞれの映画について、一言ずつ。
『ストーリー・オブ・マイライフ / わたしの若草物語』、愛することについての映画。男が女を愛する、女が男を愛する、親が子を愛する、子が親を愛する、姉妹、隣人、関わる全ての人、そして人生で出会うことが永遠にないはずのすべての人。いまだからこそ見たい、ひとつの家族、そしてグレタ・ガーウィグが奏でる愛の賛歌。
これは私たちすべての物語だ。
『WAVES』、きっかけはたったひとつの小さなふるまいだった。それくらいのことは許されると思っていたたったひとつのふるまいは、いつのまにか誰も想像もしないほど、大きく育ち、そしてWAVESを巻き起こす。自分の発言/行動ひとつひとつがもたらす影響に自覚的でありたい。ここに登場した人たちは皆被害者だったようにも見える。そして、被害者だったはずの、妹のエミリーがこうも強く生きられるのか、ということにただ勇気をもらった。
『mid90s ミッドナインティーンズ』、どれだけ最高だったか。僕たちも、mid90sに同じ時代を生きたことを誇らしく思う。
また、初めてだよ、ただ一席も空かずに、満員の映画館に居るだけで泣いてしまったのは。映画は観客全員で体験するものだ。そこにたまたま出くわした観客全員を巻き込んで、特別な時間を作る営みなのだということを思い出した。
過去のブログにあるように、大学3年生のとき、渋谷での『ストップ・メイキング・センス』、映画館で観客全員で立ち上がって、アホみたいに踊った夜を思い出す。
mid90sちょっと最高すぎた、パーカー買おうかめっちゃ迷ってるけど絶対似合わないとりあえずスケードボードほしい。spotifyでサントラ聴いて帰ろ pic.twitter.com/mCETrqJ0jE
— たなだい@映画垢 (@daichit64) September 21, 2020
『燃ゆる女の肖像』、言わずもがな、視線の映画だ。目を向けること、振り返り見つめ返すこと。隣に並び見つめ合うこと。にも関わらず、ラストシーンの視線の一方向性。彼女は震えながら、決して視線を合わせようとはしない、そこに彼女がいることがわかっているからこそ。そのシーンは、『君の名前で僕を呼んで』のラストシーン以来の、忘れがたい美しさだった。たまたま、いずれもクィア映画だったことは偶然だろうか。
アデル・エネルのWikipediaにある、このエピソードもとても好きだ。僕はロマン・ポランスキーの映画も好きで仕方ないのだが。
2020年2月28日、第45回セザール賞(英語版)で当時13歳のサマンサ・ゲイマーを強姦した罪で有罪判決を受けたロマン・ポランスキーが『J’Accuse』で監督賞を受賞したことを受け、自身も主演女優賞でノミネートを受けていた『燃ゆる女の肖像』の監督のセリーヌ・シアマと、共演者のノエミ・メルラン(フランス語版)と共に、抗議の意味を込め授賞式から退場した。エネルは退場する際、拳を突き上げ「恥を知れ!(La honte!)」と叫び、会場のロビーで皮肉を込め、拍手しながら「ペドフェリア万歳!(Bravo la pédophilie!)」と叫んだ。
『ブックスマート』、エイミーが、パーティーのカラオケで歌うアラニス・モリセット「You Oughta Know」は永遠にリピートして聞いていた。そして、いじめられっ子でもおかしくない彼女たちの存在がこんなにも肯定される世界の存在。僕の学生時代はこんなことはなかった。僕はブックスマートの高校がとにかくもうらやましく思うのだ。
『リチャード・ジュエル』、ある意味『ブックスマート』と対比的に観たい。こんなにも誠実であっても、人は見た目で、リチャード・ジュエルのようになる可能性を秘めているのだ。それでも、僕はジュエルやブライアントのように、たとえ味方がいなくなろうとも、自分の正義と信念に嘘をつかず、生きていきたいと願うのだ。
『スパイの妻』、黒沢清と濱口竜介、蒼井優と高橋一生。いま日本の映画界で最も偉大な才能たちが、ここに集まり、壮大な転覆計画を企てる。誰もが夫婦の共同作戦に見えた。それが夫によって崩れ落ちる様。愛情なのだ。
『TENET テネット』、クリストファー・ノーランもここまで来たか、というところまで来た。この映画がヒットすることは未来を信じるに十分値するものだ。
TENET意味わからんて聞いてたけど、中学生の頃からディックやアシモフのSF小説を読み耽り、学校サボってスピルバーグの映画を公開初日から観で、ノーラン映画はメメントから当然全部劇場で通い続けた俺ならいけるっしょ、とIMAX最前列で見てきた!…全くわからんくて吹いた…けど最高でした!#TENET
— アジヘル@AI医療機器アイリスCOO (@healthcareITSG) September 22, 2020
『行き止まりの世界に生まれて』、カメラが存ること、それがなければ決して映されることのなかったいくつもの瞬間があるのだな、映画というものがこの世にあることで、どれだけ世界が前を向いたか、ということを実感した。『mid90s』と連日、最高のスケボー映画を観れたことの幸せを噛み締めた。
『ミセス・ノイズィ』、最初の数十分以外、全く笑えない恐怖の映画だった。僕は、この登場人物の誰にでもなりうるな、という危機感を感じた。それでも最後は希望にまみれた。
そして、2020年は素晴らしい女優たちに多く出会うことができた。
『燃ゆる女の肖像』のアデル・エネルとノエミ・メルラン、『WAVES』のテイラー・ラッセル、『ブックスマート』のケイトリン・ディーヴァーとビーニー・フェルドスタイン、『スパイの妻』の蒼井優、『TENET』のエリザベス・デビッキ、全員の姿、ふるまい、表情、そして言葉ひとつひとつに、何度涙を流したかわからない。誰もがこの年でなければ主演女優賞となってもおかしくない素晴らしい女優の年だったように思う。
それでもMy主演女優賞は、全く迷わず、『ストーリー・オブ・マイライフ / わたしの若草物語』のシアーシャ・ローナンに捧げたい。2018年に続き、二度目の栄光。『レディ・バード』のときの魅力とは、全く違った姿を見せる彼女に、心底惚れ込んだ。
映画中、彼女が、父のためにヘア・ドネーションをしたシーン、そして廊下で崩れ落ちる姿を見ただろうか。「どうしようもなく、孤独なの」といった彼女の表情を観ただろうか。私たちのいま求められるふるまいとは、まさにこれなのだ。
主演男優賞は『mid90s』のサニー・スリッチに。彼がプロのスケートボーダーだったということに驚くばかりだ。いつまでたっても相変わらず、HipHopとスケボーとサーフィンが好きで好きで仕方ない。
最後に、ここで挙げたように、今年素晴らしい映画がたくさんあったが、それでも最も僕の人生に影響を与えたものは、演劇『人類史』であった。
人類/人類史といっても、これまで自分の人生にとって、アクチュアルなものにはなっていなかった。
しかし、この11月に『人類史』を観て、いま自分が人類/人類史という大きな流れの一部に存在するのだ、ということをはじめて感じることができた瞬間だった。
すごかった、ただもう最後の10分くらいずっと鼻水垂らしてずっと泣いていた。人類史をいま作っている。言葉、数学、伝染病、インターネット、不老不死、シンギュラリティ、連綿たる歴史を過去も未来も体感できる時代。
そして、フランスのカフェでサルトルがやったように友人と語り続けたい。#人類史 pic.twitter.com/K8l27AYYev— アジヘル@AI医療機器アイリスCOO (@healthcareITSG) October 23, 2020
いささか感傷的になってしまったが、今年はこうした言語化/文章化をもっと意識することにしている。そして、2021年も、映画とともに生きていきます。
今年も、よろしくお願いします。
▼昨年までの映画ベストはこちら(2016年以前は別ブログにリンクします、2017年はベスト10に足りる本数がなかったため作成しておりません)